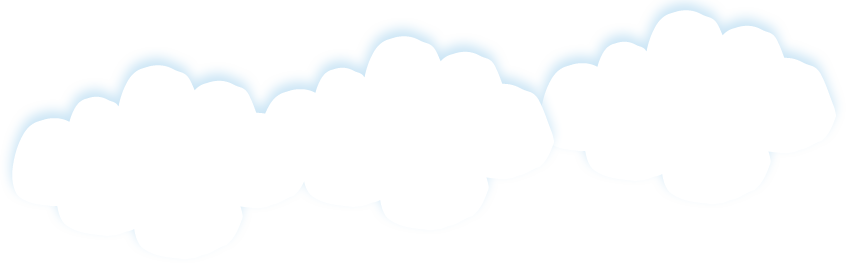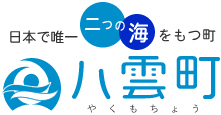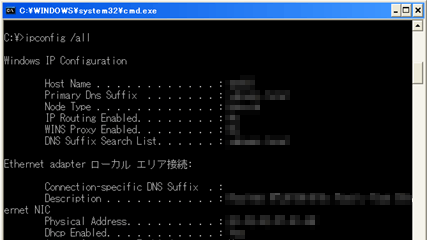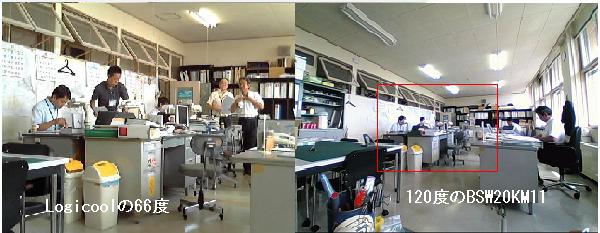明日は全道的に暑さがぶり返すらしい。もう勘弁してください!降参です!!パソコンたちも悲鳴を上げています。あるご家庭のPCからのSOSで、職場の帰り道お邪魔してきました。2台診断し、1台は何とか健康な状態まで復活できましたが、残念ながらもう1台はひん死状態でした。早急にデータのバックアップ(多分無理かな?)をお願いして、自宅への帰り道・・・?
歩道脇の垣根上に、謎の物体を発見!思わず見直しました。何と!垣根の上に「南瓜」がなっています。よく手入れされた、数十メートルもあろうかという垣根の上に、本来は地べたを這うべき南瓜のつるが所狭しと広がっています。すでに十数個の南瓜も見事になっています。すばらしい光景です!
南瓜の弦って木に登るんだっけ?新種でしょうか?そんな訳はありません。きっとオーナーがマメに弦を垣根に載せたのに違いありません。なんとなく嬉しくなる光景だったので、携帯のカメラでパチリと頂いてきました。
我が家の家庭菜園でも、この手法で南瓜の栽培をと思いましたが、近くに垣根がありませんでした。チャンチャン?!

これなら収穫も楽そうです。垣根の上の南瓜!
(投稿者:92)