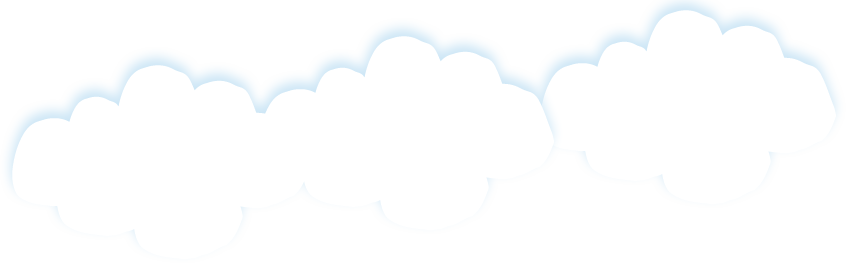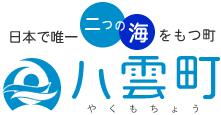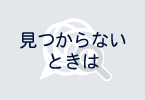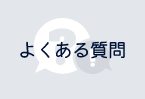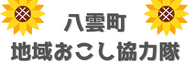北海道・三陸沖後発地震注意情報
北海道・三陸沖後発地震注意情報について
三陸沖や北海道の太平洋側の沖合(日本海溝・千島海溝沿い)では、マグニチュード(M)7クラスの地震が発生した後、東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)のように、さらに大きな地震が発生した事例が確認されています(図1)。北海道から三陸沖にかけての海域では、プレート境界のひずみがたまりやすく、巨大地震が発生する可能性が高いエリアとされています。
※先に発生した地震を「先発地震」、それに続いて発生する地震を「後発地震」と呼びます。
過去の事例
前例(1):1963年 択捉島南東沖地震
・ M7.0の地震の約18時間後に、M8.5の巨大地震が発生。
前例(2):2011年 東北地方太平洋沖地震
・ M7.3の前震の約2日後に、M9.0の本震が発生。

日本海溝や千島海溝で大きな地震が起きたとき、気象庁は「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発信されます。発表された際は、防災行政無線やホームページなどでお知らせします。後発地震に備えて、すぐに避難できる体制を整えましょう。


後発地震注意情報の発信条件
・日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の想定震源域(図1)とその周辺で、モーメントマグニチュード(Mw)7.0以上の地震が発生した場合(地震発生から約2時間後に発信を予定)
情報発信に伴い防災対応をとるべきエリア
・北海道から千葉県までの太平洋側の対象市町村
(最大クラスの地震により震度6弱以上の揺れや、3メートル以上の津波が想定される地域を基本としている)
後発地震注意情報の発信頻度(国による想定)
・おおむね2年に1回程度
後発地震注意情報の基本的な考え方
・この情報は、後発地震の発生可能性が平時よりも相対的に高まっていることをお知らせするものです。情報が発信されたら、後発地震が必ず発生するというものではありません。
・実際に後発地震が発生する確率は、世界の事例を踏まえても100回に1回程度と低いものの、巨大地震が発生した場合には広域にわたる被害が想定されています。そのため、北海道から千葉県までの広い範囲で後発地震への注意が呼びかけられます。
・この情報の発信後1週間程度は、普段通りの生活や社会経済活動を継続した上で、いつもより地震の発生に注意し、備えを徹底してください。
・国や八雲町は事前避難の呼びかけは行いませんので、後発地震注意情報によりただちに避難する必要はありません。津波避難エリア内では、地震の揺れを感じたり、津波警報等が発表されたりした場合に、速やかに避難できるよう準備をしてください。
・巨大地震は、突発的に発生することもあります。日頃から地震や津波への備えをお願いします。

北海道・三陸沖後発地震注意情報の発表方法
情報発表の流れは、先発地震による震度や津波の大きさにより大きく変わりますが、典型的な事例は下図の流れになります。

関連情報