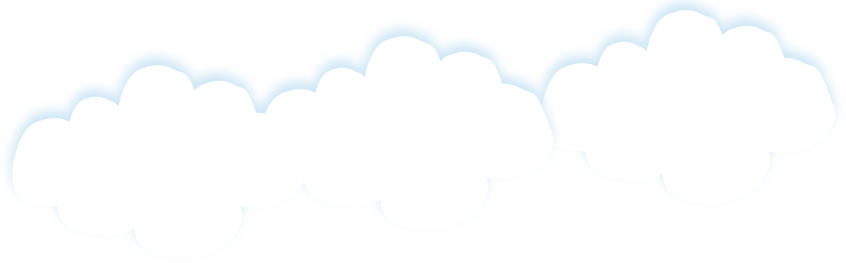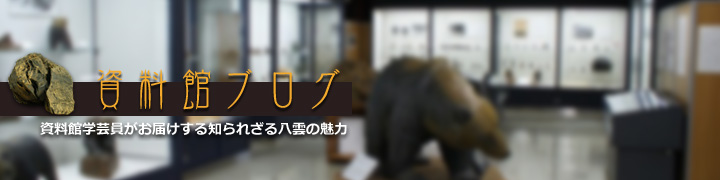連日暑い日が続いていますが、日は短くなり、草木はもう秋の気配を漂わせています。遊楽部川河口部の草原にも、ススキが穂を出し夏鳥たちの鳴く声も、段々少なくなってきています。
明治11年、徳川家開墾地に移住した兄、平川勇記(通称釜三郎)を訪ねて、明治18年4月12日熊張村(現長久手町)より来た戸田四郎は、徳川家開墾地に長期間滞在し、滞在中の出来事を『北海道往復旅行日記』に記載しています.
日記には、立岩に登り、そこから見た遊楽部川とそこに広がる開墾地の風景や山・海岸など、他の記録と違って自然についても書かれています。鳥についての記述は、日記の明治18年4月15・16日に「この頃小鳥各種深山より家辺にへ来る」、6月1日「この頃、ムク、雀、ワシ、鳥その他巣を結ぶ」と書いています。つまり、春には鳥が里(平地)に来て、初夏にはこれらの鳥が繁殖のため巣を作くると書いているのです。
当たり前のことですが、この事は今でも変わりなく見られる光景です。ただ、四郎が「山より家辺と」と表現したのは、春になると色々な鳥たちが急激に平地で見られるようになるので、山から鳥たちが来たと考えたのでしょう。秋から冬にかけて、山から平地に下りてくるウソなどの鳥はいますが、春は、繁殖のために他地域から渡ってくる鳥が多く、この事を現しているのだと思います。
遊楽部川河口の原にも、夏鳥が渡って来て、巣を作り子を育てます。8月末から9月になると、繁殖のおえた夏鳥は、子を連れ渡ってきた地域に戻り始め、夏鳥がだんだんと少なくなっていきます。10月に入ると、ハクチョウ、カモ類が、11月頃にはオオワシ、オジロワシが遙か遠くサハリンから来て、遊楽部川の鳥も夏鳥から冬鳥へと主役が変わることになります。

コヨシキリ(成鳥)スズメより小さく、繁殖期にはよくさえずる。

ノビタキ(雄 成鳥)スズメより小さく、草原によく見られる。

ノビタキ(雌 成鳥)スズメより小さく、草原によく見られる。

カワセミ (雄 幼鳥) スズメほどの大きさで、河口域でよく見かけるが飛ぶのは早い。

オオルリ(雄 成鳥)スズメより少し大きく、渓流沿に見られる。
(投稿者:ジョー問)