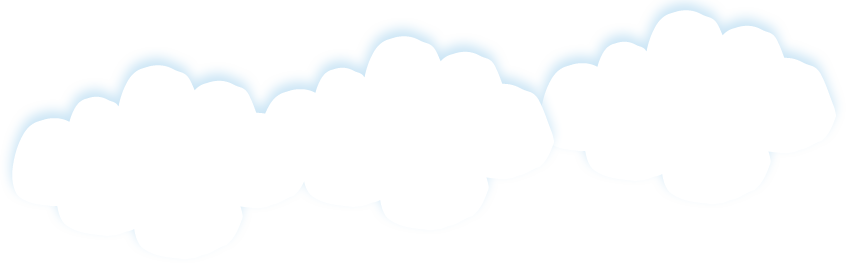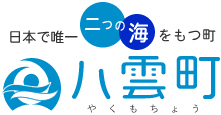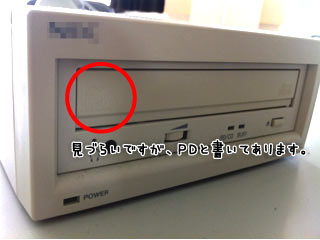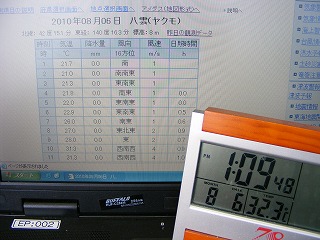ども。
暑い暑いと言いながらも、寒いよりは全然へっちゃらだなと思っている担当ちゅんです。
今日、とある職員の方からこんな質問が。
「最近地デジ対応TVを買ったんだけど、BS放送とCS放送の違いって何?」
はい、それはそもそも衛星の種類が違います。終了!
…というわけにもいかず、結局のところ「無料で見られるのがBS、お金を払って見るのがCS」という説明をして納得していただきました。ですが、この「BSとCSの違い」というのは、実際にどのくらいの人が正しく説明できるものなんでしょう。正直、私もあやふやでありましたので、ちょっと調べてみました。
まず、衛星が違うという認識は大丈夫でした。BSは『放送衛星:Broadcasting Saterite』で、CSは『通信衛星:Communication Saterite』となります。そもそも、テレビ放送に特化して上げられた衛星がBSであり、CSで直接放送が認められたのは1989年の放送法改正後から。それまでは「放送」に利用することは禁止されていて「通信」にしか認められていませんでした。今は同じような用途で使っている衛星ですが、こうした歴史があるのです。
じゃあ今は区別しないで「衛星放送」に一本化したらどうなの?と思いますが、そもそも衛星が物理的に違いますので、アンテナを向ける方向も違います(BSと同位置の東経110度にCSの衛星も上がっているので、BSのアンテナだけでもCSを見ることはできます)。一般家庭で視聴されるいわゆる「衛星放送」と呼ばれるものは、民放各社が放送しているBSと、スカパーが放送しているCSという区分けでほぼ間違いありません(CSは企業・団体向けの通信にも使われています)。BSを見るためのアンテナと、スカパーを見るためのアンテナでは方角が違いますので、双方を受信するために2つパラボラアンテナを上げているお宅もたまに見かけます。要するに衛星放送と呼ばれるものの中にBSとCSという2種類の放送があるという理屈になります。
なので、BSとCSの違いは何と言われたら、やっぱり衛星の種類が違うという話に落ち着いてしまうのです。1つのアンテナでBSとCS双方が受信できるので混乱してしまいますが、そもそも同じ110度に衛星を上げたということが画期的なことなんです。ちなみに、2011年にはBSとCS共同で東経110度軌道上に衛星を打ち上げ予定。BSは本サービス用、CSはバックアップ用とのことですが、こうなるとますます住み分けが分からなくなってきますね。

ちなみに衛星放送は地デジ難視対策最後の要でもあります。
(投稿者:ちゅん)