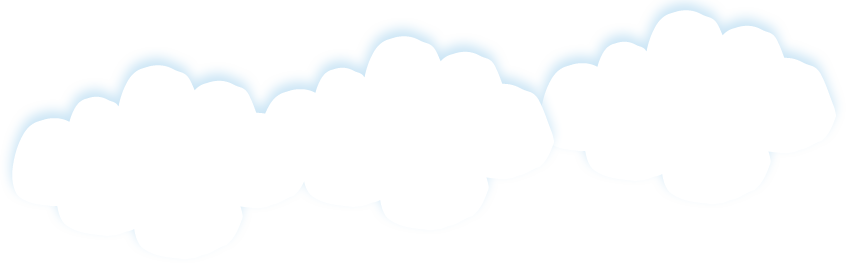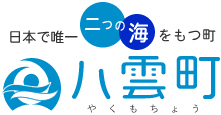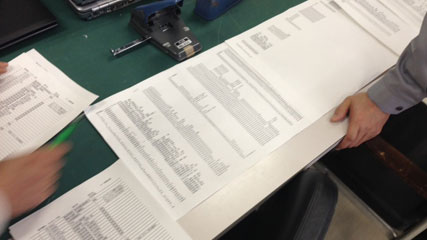さて、あまりの天気の良さにつられ?スキー場のライブカメラの撤去作業に行ってきました。「スキー場のライブカメラ始まりました」で紹介したとおり、毎年ご好評をいただいていますが、スキー場は既に今シーズンの営業を終了していました。防犯上、はたまたカメラの紫外線による劣化を防ぐために、シーズンオフには取り外すことにしています。
この所の好天で、スキー場までの道路や駐車場、ロッジ前には雪もなく、新緑は芽吹き始めていました。すっかり春です。しか~し!ゲレンデには、それなりの雪が残っています。営業中は毎日、圧雪車で固めていましたので、簡単には溶けるないようです。そんなゲレンデをよく見ると、何と!中央のBコースに新しいシュプールが数本!!!誰が滑ったのでしょうか???勿論リフトなんかは動いていません。自力で山頂まで登り、春山スキーを楽しんだに違いありません。恐るべしスキーヤー魂!?

ゲレンデにはまだ雪が・・・。春山スキーを楽しむスキーヤーも?
(投稿者:92)